フランスで人気の子どものためのガイドブック
あなたならどうする?と考えさせる L・ジャフェ、L・サン=マルク作 は、フランスの教育出版社の子どものための生活ガイド の翻訳版。

お金とじょうずにつきあう本
はじめに、
「最新のゲームソフトがどうしてもほしい」
「おけいこごとをはじめたい」の投げかけに、
3つのよくありそうな行動パターンが書かれています。
そして、よく考えてページを開きましょう!とも。
私はこの本の解説で述べられています、この部分がとても気にいています。
「子どもだからといって安易な言葉に逃げず、社会の現実をきちんと伝えることが、
今、日本でも必要なのではないでしょうか」
どうですか?子育てにおいて逃げてはいけないことがたくさんあるのですよね。
少し内容を説明しますと、 話が3つ入っています。
1つは「ほしい」って何?「必要」って何?と、子どもがわかる事例を通し、順序だて
て明快な説明があります。
消費欲が蔓延しているような現代社会で、生きるのに必要なもの、あると便利なもの、欲しいと思っていてもぜいたくなもの、など大人も2つの言葉を整理するのに役立つ内容です。
2つ目は、何でも手に入るのか?という投げかけです。
昔は手作りが多かったですが、現代社会では自分に必要なものを全て自分で作る人はほとんどいなくなりました。
今の社会ではほとんどのものをお金と交換して得ることができると、説明があります。そのとおりですが、お金の役割や現実の問題等を教えてくれる内容です。
「なぜ、お金が必要になったの?」 「どうすればお金が手にはいるの?」「誰でもお金を持っているの?」「不公平をどうしたらいいの?」という質問に、うまく答えられないわ、という時には、大いに活用できる本です。
3つ目は「価値」について。
価値観は大きく違っています。だから集団で金銭教育を行うのが難しいのです。
せめて、自分の子どもに、親として、自分の思う価値あることを伝えていけるようになりたいものです。
その前に私たち親が考える時間を作り、自分の考えを持つことが大切なんですね。
それぞれが、「おはなし」「調べてみよう」「やってみよう」の3つのステップで理解でき、子どもが自分の経験とあわせて理解していきそうなガイドブックです。
親にもぜひ一緒に読んでもらいたい本です。
読売新聞2002年11月第3週に掲載したものに加筆修正しました
これを書いています2006年の冬。
大雪でとても大変な地域がたくさんです。
雪国ってどの範囲をさすのかな?って調べてみました。
2月の最大積雪深の年平均が50センチを越えるところだそうです。
なんと、日本の53%は雪国・・・だそうで、びっくりです。
こういう時期、きっとこんなに頼りになるじょせつしゃがいてくれたら・・
そういう気持ちでまたまた読んでしまいました。

はたらきもののじょせつしゃけいてぃー
この本、特別な力を持つってすごいこと、すばらしいこと、
頼りにされるってこういうこと、期待にこたえるってこういうこと
そんなことを自然に伝えてくれるようで、雪国だけでなく読んであげたい本。
女の子や南国の子どもたちは、もしかするとピンとこないかもしれないんですけど・・・。
けいてぃーの頑張りには、
子どもたちみんなで「がんばれ〜」って声援を送ってくれそうな気がします。
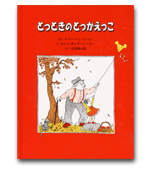
私が絵本に目覚めた1冊です。
とっときのとっかえっこ
金銭教育とはちょっと違いますが、ぜひ、おすすめしたい絵本です。
何をとっかえっこするのでしょう。
ネリーという女の子とお隣のバーソロミューおじいさんはとっても仲良し。
ネリーが赤ちゃんだったころは、ネリーがバーソロミューにベビーカーで散歩に連れて
行ってもらっていました。
月日が流れ、大きくなったネリーと年をとったバーソロミュー。
ある日、バーソロミューがけがをして、車椅子の生活に。
「散歩はおしまいだな」というバーソロミューに
「わたしがつれてってあげるもん」とネリー。
そう、役割をとりかえっこしたんです。
私はこの本の読み聞かせは絶対にできないんです。
読むたびに、毎回涙が出てしまうからです。
公的介護保険が導入されたとき、
先にこの本を読むべきよ!って思いましたね。
やさしい気持ちを育ててくれる本だなあと思います。ぜひ!
(およそ、6歳から7歳くらいから)
パンやのくまさん
ゆうびんやのくまさん
せきたんやのくまさん
うえきやのくまさん
ぼくじょうのくまさん
くまさんはいろんな仕事で大活躍です。とっても働き者。
無理に金銭教育にこじつけるつもりはありません。
いい仕事ってなんだろうって思うんです。
人のお役に立つ仕事って、きっといい笑顔でのお返しがありますよね。
今の世の中、そうでない仕事もいっぱいありそうな気がします。
それは、人を騙してでもお金を得ようとすることだったりで、
それが仕事とはいえないとは思いますけど、
そうやって、糧を得ていることってとっても悲しいなあと思うんです。
せめて、わが子は、お役に立てる仕事で、
自分の身の丈にあった生き方をして欲しいなぁなんて思いながら
子育てしています。
話が飛びますが(笑)、
「賢い消費者」の話をするときに、
「ものの値段」の後ろに、人の生活が見えるようになって欲しい、と言います。
見えるようになれば、それが適正価格であるかどうかが見抜けるようになるし、
価値のある買い物ができるようになる。
感謝の気持ちも出てくるだろうし、
何よりも ありえないだろう儲け話などには騙されないだろうと思うのです。
一生懸命に仕事をするくまさんに、失われてきたかな〜と思う勤勉さを感じます。
ペレのあたらしいふく
これも幼児期にぜひ読んであげて欲しい1冊です。
お金は出てこないんです。
「ペレは、自分の資産である羊から自分の服を作っちゃいました。」っていうお話です。
これ、りっぱな、金銭教育です!
昔々は、自分のできる技術や労働を交換し合うことって多かったと思います。
今はほとんどがお金を使って、
お金の交換手段、尺度(ものさし)という役割を活用して
合理的に必要なものを交換していますね。
子どものペレには何ができるでしょう。
洋服1枚作り上げるのに、どんな技術が必要なのでしょう。
絵だけでもわかります。
私は、最後のペレを見守るあたたかな町の人たちが大好きです。
地域で子どもを育てるってこういうことではないでしょうか。
わが家には絵本が300冊ほどあります。いえ、もっとかも。
その中に「これ、お金の教育に使える!」って思えるものがあるのです。
お金のことというより、
経済社会を伝えることができるし、
労働の楽しさ、面白さを上手に伝えるのに、
絵本からスタートがいいなあと思うんです。
大人が労働や経営を語り始めると 「大変なんだ!」って言いたがるでしょう。
だから、いいことも伝えてあげなくちゃ、
子どもたちは働くことが嫌になっちゃうと思うんです。
そこで、こんなお話で、
家族で協力して働くってことの楽しさを子どもに読んで聞かせたいなあと思いますね。
からすのパンやさん
アマゾンサイトのレビューからちょっと頂きました。
↓
カラスの町「いずみがもり」にある、1軒の売れないパン屋さん。お父さんお母さん、4羽の子ガラス、家族みんなで、楽しい形のパンをどっさり焼いた。パンを買いにやってきたカラスの子ども、おじいさん、おばあさん、そしてなぜか消防自動車、救急車、テレビのカメラマンまでやってきて森は大騒ぎに…。
おすすめの絵本の3部作です。
かあさんのいす
ほんとにほんとにほしいもの
うたいましょうおどりましょう
私が最初に読んだのは、3部作の1作目 ■ かあさんのいす でした。
長男が小学生のときですから初めてであったのは10年以上も前になるでしょうか。
この本を読んだだけでは、ちょっと辛いものがあって、
読み聞かせは気分が乗りませんでした。
なぜって?絵本の中のお母さんが疲れてて、私の姿と重なったんです。
そのころは保険会社の外務員として働いていたのでとってもハードでしたから。
でも、二男は、お母さんと子どもが一緒にイスに座っているページが好きなのでしょう、
読んで欲しいと本棚からいつも持ってきていました。
ある日、イベントの絵本の展示コーナーで、残りの2冊に出会ったのです。
■ ほんとにほんとにほしいもの
■ うたいましょうおどりましょう
すぐにわかりました、同じ作者であることは。
1ページ、1ページの隅から隅まで描かれた細やかな心遣いにも感動しましたし、
何より、人生がこの3冊に表現されている、すばらしいという思いがこみ上げ、
この本に出会って本当に嬉しくなったのです。
2冊目の『ほんとにほんとにほしいもの』が
金銭教育の絵本として取り上げられやすいのですが、
3冊そろって読んでいただきたいのです。
大人も人生を考えることができる3冊になることでしょう。
ぜひ、子どもさんと一緒に読んでいただきたいですし、
小学校の図書館にもそろえて欲しいですね。
お問合せ・ご相談はこちら
マネーじゅくは、お金に関する生涯学習プログラムを提供し 社会貢献を目指す社会起業家の集まりです。わたしたちは、個々人の特性を生かしながらオリジナル教材を使い、地域に合わせたお金の教育活動をおこなっています。
生きる力 を お金、経済の視点からアプローチ。幼児期の子どもたちから大人まで広く奥の深い「お金の教育」を研究、提案、実践しています。
「金銭管理教育」「金融経済教育」「消費者教育」「キャリア教育」「特別支援教育」「家計管理」などの分野をプロデュースしたコンテンツを持ちます。
得意なことは学習ゲームを教材にしたワークショップ。
オリジナルプログラムは各方面から評価をいただいています。
家庭経済教育メニュー
おうちdeこづかいゲーム
マネーじゅく本部
住所
〒811-0013
福岡県糟屋郡新宮町
桜山手2-12-8














